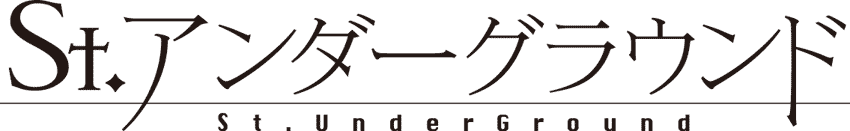「――!?」
絶句した襲撃者がいた。
その気配を感じた紗夜子はぎゅっと閉じていた目を開けた。
目の前の大気がプリズムのように輝き、ビニールのような弾力を持って震えていた。
しかしそれが何かを確認する間もなかった。紗夜子を抱えた彼は、そのまま忍ばせていたらしい短銃を手にしながら走り出したからだ。
何が起こっているかを知った者から、また周囲はパニックに陥った。その流れに乗って彼は紗夜子を走らせた。そして何事かを叫んでいたが、紗夜子には聞き取れない。紗夜子が聞き取ろうと振り返ると、怒鳴り声が届いた。
「追い付いてくるぞ、走れっ!!」
走った。曲がれと言われれば曲がった。それしか紗夜子に生きる道はなかった。
だが、黒い影が、まるで地上すれすれを走る猛禽類のように動いた。そしていつの間にか目の前には襲撃者が立っている。
紗夜子は凍った。赤い唇も、美しい姿も変わらないのに、その姿は異形だった。
「な……」
「ご機嫌よう、紗夜子。どうして逃げるのかしら?」
父の秘書エリザベスの、突き出した両手には、先程まで握られていた銃がない。だが、二つの銃口が紗夜子に向けられていた。
薬莢を輩出するためなのか、腕には穴が穿たれている。弾倉となっているらしいいくつもの筒が腕の下部分に、棘のように突き出し、肩から後ろへ銃身のような筒が数個生えている。それは呼吸や筋肉の動きのためか、きちきちといやな音を立てていた。
異形だった。華奢な白い腕そのものが、銃器なのだ。人間ではない。
――ヒューマノイド。
エデンは工学技術、コンピューター技術とロボット工学が非常に発達している。自ら両腕両足を機械化する、生体義肢の技術を利用する者も少なくないのだ。高度なコンピューター、ロボット、生体義肢になるほど高価で、上階層が独占する状態にあった。だが、人間と変わらないロボットの話など、聞いたことがない。
けれど、目の前の彼女の手足は生体義肢ではないと何故か思わずにはいられなかった。全身が機械の、機械生命体なのだと直感する。
「いつまでも逃げられるわけないわよ? だって、あなたのお家、燃やしてしまったもの」
「な……!?」
驚きのあまり絶句した紗夜子の前に、同じくエリザベスに銃を突きつけたままの男が割り込んだ。エリザベスの顔が歪んだ。
「……お父様が嘆かれるわよ、紗夜子。いつの間にこんな柄の悪い男と知り合ったの? シールドなんてものを携帯している男に、ろくな人間はいなくてよ?」
「お前、【魔女】だな」
魔女? と紗夜子が見上げるが、彼は視線をエリザベスから逸らそうとしない。エリザベスの方は、驚嘆と皮肉を交えた顔で微笑んだ。
「なるほど。その言葉を知っているということは、あなた『狩人』なのね。ご挨拶申し上げるわ」
腕が銃だというのに、その笑顔は美しい女性そのままだ。大舞台で自らの名を呼ばれたように、堂々と彼女は名乗った。
「あたくしはエリザベス。『三番目のエリザベス』。タカトオの【魔女】と呼ばれているわ。綺麗な狩人さん、あなたのお名前は?」
男は間を置いた。辺りはしんと静まり返っていた。人は逃げ出し、辺りのビルにも人影が見えない。車道の車は乗り捨てられ、ヘッドランプがジグザクに交差している。街の灯りが、夜で空虚に光っている。
紗夜子は彼を見た。筋肉のついた腕、そこを彩る刺青。伸びた髪。彼の後ろにはもう一丁の銃。
――もう一丁の銃。
そして、耳を澄ませた。この状況で、彼の名前を聞こうとし、両者の動きを見定める。
彼は、ゆっくりと口を開いた。
「俺は、アンダーグラウンド。お前たちが、UGと呼ぶ者の一人だ」
次の瞬間紗夜子は彼の後ろのポケットから銃を抜き取った。素早く安全装置を解除し、後先考えず撃ち出した。
紗夜子の銃弾はエリザベスのすぐ側を走った。こちらへ跳躍したエリザベスの脇腹をかすったのは男の銃弾で、彼女は体勢を崩す。
しかし次の瞬間横に飛んでいた。その場所に銃痕が走る。
ちっと彼が舌打ちした。どうやらビルの上に男の仲間の狙撃手がいたらしい。紗夜子が見上げた時にはすでに見当たらない。
すると紗夜子は後ろへ引き倒され、直後激しい銃声が始まった。背後にはすでに何人もの戦闘員がいて、一斉に攻撃を始めたのだ。エリザベスはもう一度、今度は高く飛び、ビルの上へ逃げていった。タタタタ、と銃弾が追ったが、彼女の姿はあっという間に見えなくなった。
硝煙の匂いが、夏のように夜に漂っていた。季節と状況なら花火をやっていたと錯覚しそうだが、そういうわけにはいかなかった。
紗夜子は銃を握りしめたままへたり込んだ。
「…………っ」
詰まっていた息がようやく吐き出された。今更に震えが来て、がちがちと歯が鳴った。すると、彼がぽんと頭に手を置いた。
「咄嗟によく撃てたな。やるじゃねえか」
「……なんとか、一矢報いないとって……」
ポケットにもう一丁銃が入っているのを見て、思ったのは『あれを使えばなんとかなる』という、無茶苦茶な確信だった。だから彼の存在がなかったら、紗夜子はエリザベスに殺されていただろう。
「よく頑張った。ゆっくり、深呼吸しな」
吸って吐く。吸って、吐く。彼の手が紗夜子の手に添えられる。銃から指が解け、取り落としそうになったそれを彼の手が受け止めた。安全装置を戻し、硝煙のにおいがする手で紗夜子の頭をかき混ぜた。
「大丈夫かぁ、トオヤ」
「ぎりぎり。間に合ってくれてよかった。サンキュ、ジャック」
派手なシャツに見覚えがある。現れたのは、同じく今日二度目の男性だった。
「あれ、お嬢さん……」
「【魔女】に狙われてた。家燃されたってよ」
「ええっ!?」
見上げると、驚きの声を上げた彼はひとつ咳払いし、優しく微笑んだ。
「また会うたな、お嬢さん。そんな顔せんでも大丈夫やで」
ぽんぽんと大きな手が肩を叩く。
「俺らで保護した方がええか?」「そのつもりだった」と二人が言葉を交わす。立てるかと手を差し出され、起こしてもらう。
立ち上がっても、その手が、なかなか離せなかった。
「……」
見捨てられたら死んでしまうと感じていたからかもしれない。だからか、彼は手を握って離さないことには何も言わなかった。
「狙われる理由、聞いてもいいか」
首を振る。「分からない……」と答えた。本当に、分からなかった。でも、誰が命じたのかは明白だったろう。ジャックが首をひねりながら言ったのだ。
「タカトオの魔女……高遠氏がお嬢さん狙う理由って、なんやろうか?」
その言葉で、紗夜子は、絶望の淵に立っている気がした。
「……取りあえず、戻ろか。いつまでもここにおられへん。警察来るやろうし。俺ら素顔やし」
手を引かれるまま歩き出す。紗夜子の思考は、ぐるぐると回っていた。
(エリザベスを使えるのは父さんしかいない。エリザベスに命じられるのは、父さんだけだ……)
暗闇を歩いている気分だった。家が燃やされたなら、紗夜子に行くところはない。エリザベスが狙っているなら、フィオナやナスィームのところにも行けない。きっと監視がついているだろう。どうやって逃げればいいのか。このまま、闇に殺されるしかないのか。
ああそれはきっといつかの罰なのだ……。
「エリシア」
ぼんやり見上げる。
「サヨコって誰だ」
躊躇や、この先のことを考えたわけではない。ただ口が重くて、間が空いた。厳しくはないが追究する二人の目から俯き、のろのろと答えた。
「……私の名前。私の、本当の名前」
「サヨコ、なんつーんだ」
「……タカトオ。高遠紗夜子」
ジャックが息を呑んだ。だが尋ねた彼は変わらなかった。でも二人とも解釈したに違いなかった。
父親が、娘を暗殺しようとしたのだ、と。
ぼうっと目を上げると、視線が混ざった。紗夜子は聞いていた。
「あなたたちは……?」
派手な彼が言う。笑みを浮かべて。
「俺はジャック。よろしゅうな。苗字は勘弁してや。UGに苗字はないからな。なあ、サヨちゃんって呼んでもええかな?」
ぼんやりとしていて返事をしたかもはっきりしないが、ジャックは紗夜子に向かってにっこり笑ってから、傍らの彼を見た。彼はただ一言名乗った。
「トオヤ」
UGと称される人々は、多くはエデンの表に出てこられない者たちで、素性を隠す傾向があるらしい噂は知っていた。元々戸籍が怪しい人もいるという。存在しない者たち、それがUGだ。だから、彼らが本当にUGであることは、少しだけ複雑な気持ちにさせた。紗夜子はふっと笑った。
(第三から第一へ……そこから更に落とされる、か)
いつの間にか辺りはすっかり暗くなっていた。灯りの少ない方へと進んでいるせいもある。
どこか見知らぬ建物の中に入っていく背中を見ていて、後ろをとんと突かれて慌てて続く。長い階段があり、横穴みたいな長い廊下があった。低く何かが稼働している音がする。
何かを入力するようなプッシュ音がして、目の前の壁が動いた。扉だったらしい。ジャックの派手なシャツを暗闇の道標にして進んでいくと、ぽつりぽつりとライトが灯った。紗夜子は驚いて立ち尽くした。
そのライトが灯る長い道は、暗く寂しい。だが、あるところから無数の灯りと人の声が溢れ始める。
地下に緩やかに下る坂、いくつかの細い通り。建物が密集し、空は見えないが、青いランプが高いところで光っていた。そして、まばゆい広告や看板のネオン、店の明かり。
それらの光が輝いている様は、第一階層の歓楽街と変わらない。ぎらぎらと看板のライトが瞬き、どこから持ってきたのかケーキ屋のマスコット人形が首を振っている。ネットカフェの看板、居酒屋のメニューの看板、ゲームセンターらしきどんどんという音と、パチンコ店のじゃらじゃらという音。
立っているのは派手な化粧の女性たち。人相の悪い男たち。道ばたで座り込んだ若者。浮浪者のような老人。聞こえてくるのは客引きや、酒場の声のようだ。煙や酒、揚げ物のにおいがほんのり漂っている。
街が、こんなところに出来上がっている。詰め込まれているような印象の分、凝縮されているようで灯りと闇が濃く感じられた。ここは、エデンの地下のはずだ。三段重ねの階層都市。
犯罪者の巣窟、どこにも行けない、存在しない人々が巣食う、幻の階層が、エデンのどこかにある、そんな都市伝説が脳裏を駆け巡る。
立ち尽くす紗夜子を追い越して行ったトオヤが振り返り、ジャックがにっと笑いながら、大きく腕を広げて茶目っ気たっぷりに指し示した。
「ようこそ。我らが地下世界、アンダーグラウンドへ!」
< ■ >
<< INDEX >>